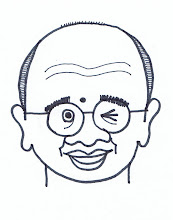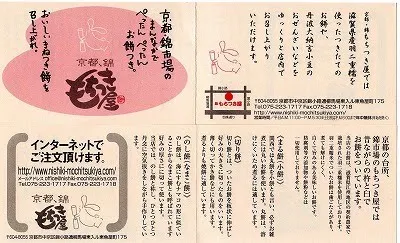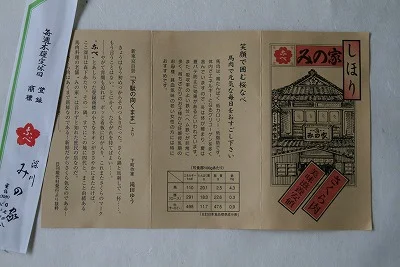管理人は色鉛筆を使う都合で、机上に鉛筆削りを置いている。
それがこれ! ドイツ STAEDTLER社製。

手で鉛筆を回して削るタイプ。

ばらしてみた。企業にいるときはいつも関連製品を「バラシズム」と言って、ばらしてみては、良い点を学んだ。

ドイツ製だから、無駄の無い設計をしているのだろうな・・・
と思いながら細部を見てみた。

プラスチックの弾性をうまく利用している。
そして左側の部品の「PRESS」のところには、
金型設計の工夫(倒れピン)で凹部を設けて、右の部品をとめている。
ねじなし設計だ!

透明蓋の「ヒンジ(蝶番)」部分は、金型のすり合わせで、
「パチン」とはめ込むだけで、「ヒンジ」を構成している。
プラスチックの特性を活かした「無駄」の無いデザインだ。
以上は、プラスチックでデザインする時の常識ではあるが、知らない人も多いので、たまにはモノをバラバラにしたら勉強にナリマッセ!
元通りになる自信がないときはヤメトキヤ!
最後に不満を少し・・・
一番右の青鉛筆は、日本の鉛筆削りで削ったもの。
右から2~4番目までは、本鉛筆削りで削ったもの。

左のシャープペンシル等と比較すると「短い」。
それでなんなの? と言われても何にもアリマヘンが・・・
でも、なんとなく短いのが気に食いませんのや! 短足の管理人より。